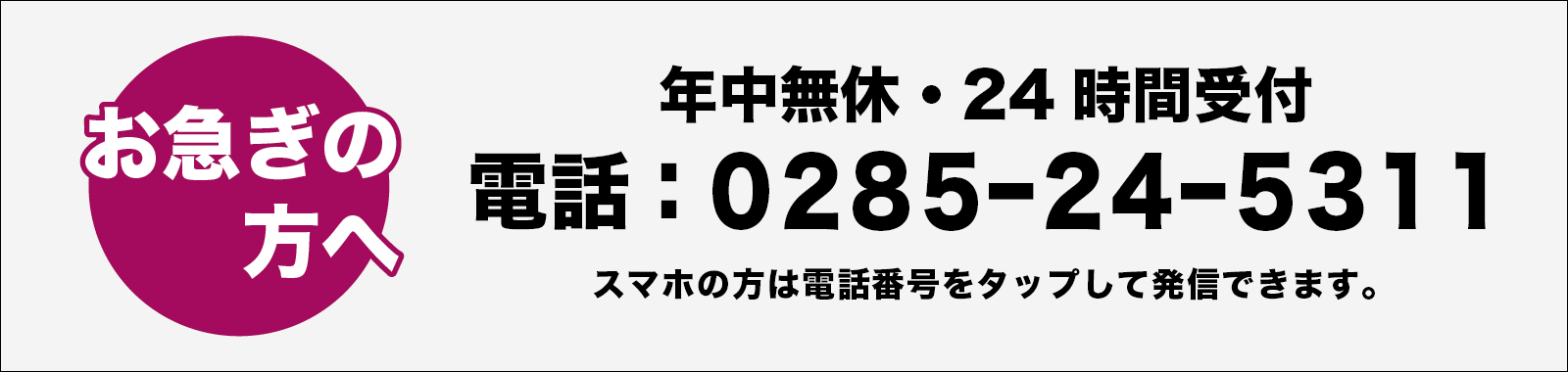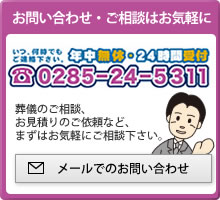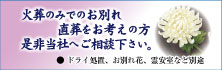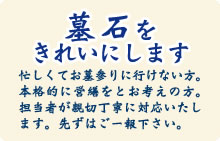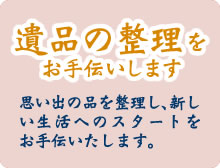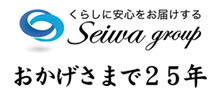年別アーカイブ: 2024年
葬儀豆知識No.2060 「 忌中・喪中の違いやマナー編 」 喪中・忌中に避ける・遠慮すべきこと ②
2024年5月25日 ニュース
例 忌中や喪中に控えるべきこと ※ 神社への参拝 忌中の期間は神社への参拝は控えます。 安産祈願やお宮参り、七五三・成人式などが忌中と重なった場合は極力控えるようにしましょう。 どうしても判断が付かない場合は神社に相談し …
葬儀豆知識No.2059 「 忌中・喪中の違いやマナー編 」 喪中・忌中に避ける・遠慮すべきこと ①
2024年5月24日 ニュース
忌中・喪中にある場合、故人の死を悼みその冥福を祈ることから慶事などは避けるという考え方があります。 これらのことは、必ずしもしなければならないというわけではありません。 一般的に避けた方が良いとされているのは、結婚式への …
葬儀豆知識No.2058 「 忌中・喪中の違いやマナー編 」 喪中と忌中の違いとは? ③
2024年5月23日 ニュース
※ なぜ身を慎むのか? 忌中や喪中の期間、どうして身を慎まなければならないでしょうか? そこには2つの理由が考えられます。 * 死の穢れを封じ込めるため ひとつは [死穢] という考え方です。 古代から日本 …
葬儀豆知識No.2057 「 忌中・喪中の違いやマナー編 」 喪中と忌中の違いとは? ②
2024年5月22日 ニュース
※ 自主的に行動を慎んで故人の冥福を祈る喪中 忌中は死を忌み嫌う社会的な強制力が働いていたのに対し、喪に服するというのはどちらかというと自主的な行為となります。 昔の考え方では、生活を慎んで故人の冥福を祈るという意味があ …
葬儀豆知識No.2056 「 忌中・喪中の違いやマナー編 」 喪中と忌中の違いとは? ①
2024年5月21日 ニュース
※ 社会から穢れを隔離 喪中としばしば混同されるのが忌中です。 忌中というのは、身近に不幸があった人がその穢れがある間は社会的な活動を控えるというものです。 かつて死が穢れとされていたころの習わしの名残で、死がほかの人に …
葬儀豆知識No.2055 忌中・喪中の違い その期間の事柄
2024年5月20日 ニュース
身内に不幸が起きてから、その遺族が身を慎む一定期間のことを忌服 (きふく) または服忌 (ぶっき) といいます。 この忌服の期間を [喪中] と呼び、この期間は故人の冥福を祈りお祝い事など派手なことは控え、慎ましい生活を …
葬儀豆知識No.2054 「 守り刀の目的と必要性編 」 まとめ
2024年5月19日 ニュース
守り刀の目的・使い方・必要性についてお伝えしました。 日本には、災厄は悪霊や厄神によってもたらされるという言い伝えが各地にあります。 こうした魔物の来訪を防御し、退散させたいという願いを込めてさまざまな儀礼や呪術が生まれ …
葬儀豆知識No.2053 「 守り刀の目的と必要性編 」 守り刀とろうそく
2024年5月18日 ニュース
お線香や守り刀と同様に故人を守るために必要である [ろうそく] があります。 ろうそくの場合は [故人が道に迷わずあの世にたどり着けるように] ・ [火を嫌う獣が近づかないように] という意味を持っています。 神秘的な輝 …
葬儀豆知識No.2052 「 守り刀の目的と必要性編 」 守り刀とお線香
2024年5月17日 ニュース
お線香・お香は仏式の葬儀に付きものです。 これは守り刀と同様に故人を守るためのものでした。 香りは故人の食べものと考えられていたことであり、お香を焚くことで死臭を紛らわせて野の獣を近寄らせないようにすること、お参りする人 …
葬儀豆知識No.2051 「 守り刀 目的と必要性編 」 守り刀が廃れていった理由 ②
2024年5月16日 ニュース
※ 宗教に囚われない葬儀のかたち。 宗教への帰属意識の薄れと共に、現在は仏教・神式にとらわれないで葬儀を行う場合もよく見られるようになりました。 これは [仏教・神式以外の宗教などで葬儀を行う] こととはイコールではあり …